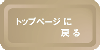| 過去の講演の記録 3 |
| 平成17年9月20日~令和5年3月14日までのメイン授業 |

令和5年3月14日(火)
修了記念講演
本学理事長 山田祥次 先生

令和5年3月7日(火)
①大阪市立自然史博物館外来研究員友の会会長 鍋島靖信 先生「大阪湾のさかな達②」
②大阪教育大学名誉教授 山田勝久 先生「遣隋使・遣唐使の活躍」
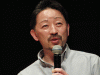
令和5年2月28日(火)市民公開セミナー(南海浪切小ホール)
①和歌山大学教育学部准教授 彦次 佳 先生「おとなのスポーツで人生を豊かにする」
②西大和学園教諭 浮世博史 先生「もうひとつ上の日本史・近代編」③

令和5年2月21日(火)
南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生「近未来-日本の可能性」⑮
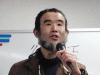
令和5年2月14日(火)
佛教大学非常勤講師
柴田広志 先生「西洋古代史ギリシャ・ローマ」

令和5年2月7日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生『菅原道真 異聞:御霊 から学問神へ』

令和5年1月31日(火)
美術評論家
岩佐倫太郎 先生「大阪の日本画展 他」― 大阪中之島美術館 ―
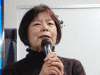
令和5年1月24日(火)なにわ創生塾副理事長
森田登代子 先生 シリーズ:女性から見た江戸時代③

令和5年1月17日(火)
①歌手、作詞・作曲家 加藤ヒロユキ 先生「人間いたるところに青山あり」
②日経xwoman副編集長 小田舞子 先生「心をくじく駄言を無くすために」
③京都大学名誉教授 大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」⑭

令和5年1月10日(火)新春公演
謡曲クラブ講師
坂口宏子 先生「謡曲と仕舞」
特別参加:謡曲クラブのみなさん

令和4年12月13日(火)
①京都大学人間・環境研究家教授 中嶋節子 先生「都市と建築の歴史」
②毎日新聞学芸部専門編集委員 畑 律江 先生「有吉佐和子さんの書かれた演劇について」
③2020東京パラリンピック・アーチェリー出場 上山友裕 先生「夢と目標について」

令和4年12月6日(火)
大阪工業大学工学部准教授
瀬尾昌孝 先生「私たちの身近なパートナー<人工知能>」

令和4年11月29日(火)
同志社女子大学講師
アンドレ・アンジェイ 先生「ヨーロッパ事情③」-フランスの一年の生活を彩る祝祭のイベント-
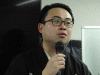
令和4年11月22日(火)
浪曲師
真山隼人 先生「闘病記~死んでたまるか」

令和4年11月15日(火)
関西大学社会安全学部准教授
城下英行 先生「生活の中の防災を活かす」
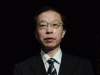
令和4年11月12日(土)市民公開講座(南海浪切小ホール)
①第一部 講演会「『米中新冷戦』で緊迫するアジア情勢」ジャーナリスト・関西学院大学非常勤講師 近藤 伸二 先生
②第二部 コンサート ボーカリスト プリンセスmaya さん ピアニスト アルベルト田中 さん バイオリニスト 武田基邦 さん
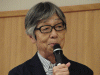
令和4年11月1日(火)
美術評論家
岩佐倫太郎 先生「『ボストン美術館の浮世絵展』の楽しみ方」

令和4年10月26日(水)
神於山保全クラブ
田口雅士 先生「里山保全活動を続ける楽しさ」

令和4年10月19日(火)
ゲームクリエーター
稲船敬二 先生「稲船流コンセプト仕事術」

令和4年10月4日(火)
南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生「近未来─日本の可能性」⑭

令和4年9月20日(火)
①なにわ創生塾副理事長 森田登代子 先生「明日へひょうひょう」
②上方文化評論家 福井栄一 先生「天神さんの虚像と実像;道真、死して神となる」
③同志社女子大学講師 アンドレ・アンジェイ 先生「ヨーロッパ事情②」-ヨーロッパ産業革命から生まれた近代美術-印象派を中心として-

令和4年9月6日(火)
①京都大学名誉教授 大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」
②西大和学園教諭 浮世博史 先生「もう一つの日本史②」
③俳優・タレント 山田雅人 先生「山田雅人・かたりの世界」

令和4年8月23日(火)【市民公開授業】
フラ講師・LUANA Hula Studio主宰
稲船理江 先生 HULAフラダンス~心と体を元気に~

令和4年8月16日(火)
元産経新聞台北支局長
吉村剛史 先生「海洋国日本を取り巻く国際諸問題③」

令和4年8月2日(火)
歴史研究サークル南木倶楽部全国代表 南木隆治 先生
「近未来─日本の可能性」⑬

令和4年7月12日(火)市民公開セミナー(南海浪切小ホール)
①僧侶 草薙龍瞬 先生「僕がブッタに出会うまで 出家・草薙龍瞬の道のり」
②聖徳太子没後千四百年御遠忌・記念フォーラム「シルクロード 仏陀の道から太子の法隆寺へ」
元NHKチーフアナウンサー 児島建次郎 先生
大阪教育大学名誉教授 山田勝久 先生
西大和学園社会科教諭 浮世博史 先生
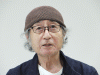
令和4年6月28日(火)
相愛大学客員教授
前垣和義先生「大阪のおばちゃん学」
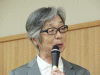
令和4年6月21日(火)
美術評論家 岩佐倫太郎 先生
「来日するフェルメール《窓辺で手紙を読む女》と、ドレスデンの名画たち」

令和4年6月7日(火)
①浄土宗西光寺住職 寺尾昌治 さん「人生に彩りを」
②フランス語講師 アンドレ・アンジェイ 先生「ヨーロッパ事情」-日本と比較して-
③-学生発表-「高野山でのひと時」 39期生 堀尾崇信 さん
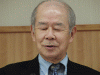
令和4年5月30日(火)
桃山学院大学非常勤講師
檜本多加三 先生「鎌倉時代のはじまり」
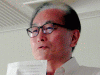
令和4年5月24日(火)-学生発表-
44期生
山中 薫さん「巨大地震に備えよ」~私のyoutubeも少し~

令和4年5月17日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「歌舞伎のABC」
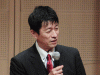
令和4年5月14日(土)第10回 市民公開講座 (泉佐野市文化会館 エブノ泉の森ホール 小ホール)
①山田雅人 さん「山田雅人・かたりの世界」
②ピアノ演奏 宮崎 剛 さん
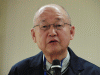
令和4年5月10日(火)-学生発表-
42期生 塩田 鉄 さん「エネルギーについて」
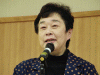
令和4年4月26日(火)
①毎日新聞学芸部専門編集委員 畑 律江 先生「OSKの歴史と特徴について」
②京都大学名誉教授 大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」⑫
③Doujima Sake Brewery UK&CO CE0 橋本清美 先生「日本文化の世界への発信」

令和4年4月19日(火)
①西大和学園教諭 浮世博史 先生「もう一つ上の日本史」
②なにわ創生塾副理事長 森田登代子 先生「遊楽としての近世天皇即位式」

令和4年3月23日(水)仏教特別講演会
僧侶・著述家 草薙龍瞬 先生
「『心の出家』で究極の健康を手に入れる」

令和4年3月15日(火)
本学理事長
山田祥次 先生 修了記念講演

令和4年3月8日(火)
南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生「近未来-日本の可能性」
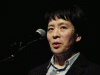
令和4年3月1日(火)市民公開セミナー(南海浪切小ホール)
①和歌山大学教育学部准教授 片渕美穂子 先生「季節の健康法ー江戸時代の養生論からー」
②大阪国際大学・短期大学部教授 阪口葉子 先生「航空会社100年の歴史・そして更なる発展」
③元NHKチーフアナウンサー 児島建次郎 先生世界遺産シリーズ⑨「東大寺・お水取り」
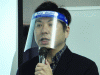
令和4年2月22日(火)
大阪河崎リハビリテーション大学博士
今岡真和 先生「要介護とならない様に」

令和4年2月15日(火)
日本看取り士会・看取りステーション「たんぽぽ」滋賀所長
西河美智子 先生「人としての尊厳を守るために」
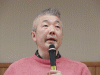
令和4年2月10日(木)
上方文化評論家
福井栄一 先生『蝶の不思議:生態と文化誌』
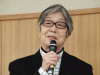
令和4年2月2日(水)
美術評論家 岩佐倫太郎 先生
「中之島周辺の美術館情報」― 中之島美術館開館に伴い ―

令和4年1月18日(火)
①薬師寺副住職 生駒基達 先生「般若心経とその心」
②京都大学名誉教授 大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」⑪
③米本合同税理士法人・税理士 吉岡智行 先生「寸劇で学ぶ楽しい相続」~誰もがいつかは迎える相続改めて学びませんか?~

令和4年1月11日(火)
米国人講談師
旭堂南春 先生 新春公演

令和3年12月14日(火)
全体授業①GHエデュケーション 鳴尾真平 先生「毎日を楽しむ豊かな『雑談力』を身につけよう!」
全体授業②39期生 堀尾崇信 さん-学生発表-「高野山でのひととき」
全体授業③在大阪スリランカ民主社会主義共和国名誉領事 D.W.アルッガマゲ 先生「スリランカ事情」
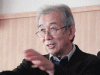
令和3年12月9日(木)
大阪市立自然史博物館外来研究員友の会会長
鍋島靖信 先生「大阪湾のさかな達」

令和3年11月18日(木)
環境保全家
泉原一弥 先生「自然環境保護の意味」
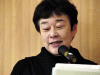
令和3年11月9日(火)
毎日新聞学芸部専門編集委員
畑 律江 先生「上方歌舞伎の女たち~片岡秀太郎さんを偲んで」

令和3年11月7日(日)
第9回市民公開講座(南海浪切大ホール)
第一部 講演会 評論家 石 平 先生「中国の国内情勢と米中・日中関係」
第二部 ダンス 岸和田3校によるダンス共演、久米田太鼓部とのコラボ(久米田、和泉、岸和田産業高校総勢140人出演)

令和3年10月19日(火)
①京都大学名誉教授 大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」⑩
②上方文化評論家 福井栄一 先生「もののけが岸和田にやってきた」
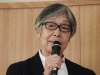
令和3年10月5日(火)
美術評論家
岩佐倫太郎 先生「ゴッホとマティス」―印象派を超えて―
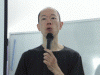
令和3年9月21日(火)
大阪工業大学教授
鳥居 隆先生「宇宙の中の私たちと私たちのいる宇宙」
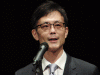
令和3年9月20日(月・祝)第8回 市民公開講座 阪南市立文化センター(サラダホール 大ホール)
第一部講演会 京都大学iPS細胞研究所未来生命科学開拓部門副所長・教授 齊藤博英 先生「iPS細胞とRNAが拓く未来の医療」
第二部 筝曲コンサート 琴:辻栄恵都 さん尺八:川崎貴久 さん

令和3年9月15日(水)
元産経新聞台北支局長
吉村剛史 先生「海洋国日本を取り巻く国際諸問題②」
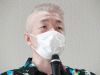
令和3年9月7日(火)
①上方文化評論家 福井栄一 先生「笑いの文化誌」~ココロもカラダも健やかに~
②京都府立大学准教授 井上直樹 先生「朝鮮に造られた日本の城-文禄・慶長の役の一断面-」
③俳優・タレント 山田雅人 先生「山田雅人・かたりの世界」
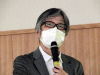
令和3年8月17日(火)
美術評論家
岩佐倫太郎 先生「琳派と印象派」―東西交流のドラマ―
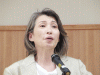
令和3年8月10日(火)
元 関西テレビアナウンサー
森田 恵 先生「おおさか すっきやねん」
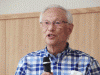
令和3年8月3日(火)【全体授業】
①大阪大学名誉教授 長谷川 晃 先生「縄文から飛鳥にかけて育成された日本人の『心』と『形』」
②京都大学名誉教授 大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」⑨
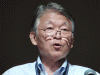
令和3年7月27日(火)【全体授業】南海浪切小ホール
①阪南市市長 水野謙二 先生「公民協働のまちづくり」
②当時統合航空統制所長・元陸将 金丸章彦 先生「東日本大震災の記憶」
③関西大学非常勤講師 横山輝樹 先生「江戸の人物像」④─ 池田光政 ─
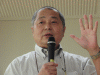
令和3年7月21日(火)
関西空港税関考査官
七村義人 先生「税関行政と密輸動向」
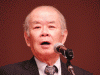
令和3年7月13日(火)【市民公開セミナー】南海浪切小ホール
①桃山学院大学エクステンションカレッジ檜本多加三 先生「女性から見た日本史ー和泉式部と平安王朝の女性たち」
②毎日新聞学芸部専門編集委員 畑 律江 先生「坂田藤十郎さんの仕事~『一生青春』を座右の銘に」
③講談師 旭堂南春 先生「米国人の私が講談師になった理由(わけ)」
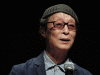
令和3年6月29日(火)【全体授業】南海浪切小ホール
①大阪切子保存会 高橋太久美先生「切子の歴史と大阪切子」
在籍者表彰
②杉原富人 先生・木村元廣 先生「新型コロナウイルス禍の逆転発想」-図書館から岸和田ルネッサンス-
③歴史研究サークル南木倶楽部全国代表 南木隆治 先生「近未来─日本の可能性」⑩

令和3年4月20日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

令和3年3月9日(火)
南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生「近未来-日本の可能性」⑨
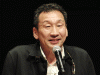
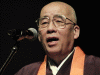

令和3年3月2日(火)【市民公開セミナー】南海浪切小ホール
①上宮高等学校卓球部顧問 河野正和 先生「オリンピックの卓球観戦の方法」
②高野山大学名誉教授 清凉院住職 静 慈圓 先生「現代中国によみがえる空海」
③関西大学非常勤講師 横山輝樹 先生「江戸の人物像」②-大久保彦左衛門-
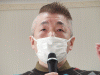
令和3年2月10日(水)
上方文化評論家
福井栄一 先生「小野小町は美女だったのか」

令和3年2月3日(水)
元産経新聞台湾支局長
吉村剛史 先生「海洋国日本を取り巻く国際諸問題」

令和3年1月26日(火)
海星病院看護部
正田美紀 先生「最期まで自分らしく生きる【人生会議】をしていますか」
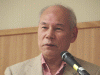
令和3年1月19日(火)【全体授業2】
京都大学名誉教授
大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」⑧

令和3年1月19日(火)【全体授業1】
ビジネスマン育成塾代表
野宗邦臣 先生「描こう!海洋国家日本の肖像!」─「日本の領土」を中心として─

令和3年1月12日(火)
新春コンサート
チェロ・ピアノコンサート
伊石昂平さん & 伊石有里さん
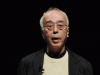
令和2年12月12日(土)第7回市民公開講座
第一部 講演会 からすま和田クリニック院長
和田洋巳 先生「がんはどうしてできるのか?ガンにはどう対処すればよいのか?」
第二部 落語寄席 笑福亭松枝 笑福亭縁

令和2年12月8日(火)【全体授業2】
大阪大学名誉教授
長谷川 晃 先生「古代日本史が生み出した日本人の心」-魏志倭人伝を読み直す -

令和2年12月8日(火)【全体授業1】
歴史研究サークル南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生「近未来-日本の可能性」
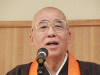
令和2年11月17日(火)
高野山大学名誉教授
静 慈圓 先生「輝いて生きる」

令和2年10月27日(火)
テレビ岸和田取締役社長
米田智範 先生「時代は4Gから5Gへ」
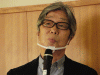
令和2年10月20日(火)
美術評論家
岩佐倫太郎 先生「お出掛け美術館」この秋の美術展、イチ押しとニ押しはこれ!
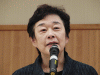
令和2年10月13日(火)【全体授業2】
毎日新聞学芸部専門編集委員
畑 律江 先生「上方喜劇の系譜とその魅力」

令和2年10月13日(火)【全体授業1】
公益社岸和田エリアマネージャー
香川一彦 先生「今どきの葬儀事情」
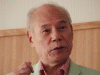
令和2年10月6日(火)
京都大学名誉教授
大石 眞先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」⑦

令和2年9月8日(火)
歴史人物研究家
加藤昌夫 先生「日本の美と心」
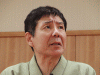
令和2年9月1日(火)【全体授業2】
落語家
桂 茶がま さん「笑いと健康 」

令和2年9月1日(火) 【全体授業1】
民話語り部
吉川裕子 先生「東日本大震災の記憶と福島民話」
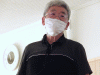
令和2年8月25日(火)
環境省自然公園指導員
田中正視 先生「日本のもり【現在過去未来】」
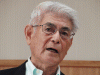
令和2年8月18日(火)
元関西経済同友会・安全保障委員会副委員長
田中克彦 先生「みんなで考えよう安全保障」

令和2年8月11日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「京・大阪にみる陰陽師 安倍晴明の足跡」

令和2年8月4日(火)
第6回市民公開講座(南海浪切大ホール)
第一部 講演会 関西大学非常勤講師 横山輝樹 先生「徳川吉宗の生涯」
第二部 コンサート「チェロとピアノで奏でる名曲アルバム」 チェロ 伊石昂平さん・ピアノ 伊石有里さん

令和2年7月28日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生八木亜夫の「世相を斬る」
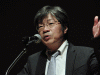
令和2年7月14日(火)
近畿大学教授
三谷 匡 先生「2万8千年前のマンモスのDNAは果たして目覚めるか?」

令和2年7月6日(月)
京都大学名誉教授
大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」⑥
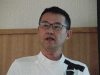
令和2年6月30日(火)
岸和田徳洲会病院理学療法士・リハビリテーション科室長
前 宏樹 先生「腰や関節の痛みの予防」

令和2年6月23日(火)
歴史研究サークル南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生「近未来─日本の可能性」⑦
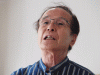
令和2年6月16日(火)
日本工芸会正会員
古野幸治 先生「トランプ大統領へのプレゼント 瑠蒼釉鉢の逸話」

令和2年6月9日(火)
カラーコーディネーター
日高かほり 先生「色のかたち新しい自分に出会う」
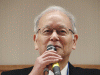
令和2年2月25日(火)
本学学長
鶴田隆志「Olympic・Scene」― from1896to2020 -
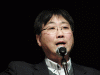
令和2年2月21日(金)市民公開講座
富山大学教授
中井精一 先生「泉州弁『だんじり』が守った」

令和2年2月4(火)学生発表
36期生 國廣英夫 さん「どうする空き家」

令和2年1月28日(火)
本学理事・社会福祉法人西谷会理事長
山田哲明 先生「終(つい)のすみ家は」
14:40~岸和田徳洲会病院総長
東上震一 先生「心臓血管外科の新しい治療」~体にやさしい心臓の手術・心臓血管病の話~

令和2年1月21日(火)
毎日新聞大阪本社元G3部長
木田智里 先生「東日本大震災9年」
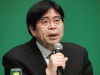
令和2年1月14日(火)第5回市民公開講座(南海浪切小ホール)
第一部 講演会 大阪市立大学名誉教授 毛利 正守 先生「日本書紀における天照大神及び皇孫降臨―古事記と比較しつつー」
第二部 コンサート新春~二胡の調べ 二胡奏者 雪本 直子 さん*蘇州夜曲 *夜来香 *ふるさと他

令和2年1月7日(火)
新春の舞「年の初めを舞楽で祝う」
原笙会代表 生川純子 さんら
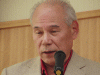
令和元年12月10日(火)
京都大学名誉教授
大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」⑤
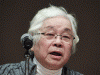
令和元年12月3日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

令和元年11月26日(火)
学生発表「ネパールへの招待」
第1部 「わが祖国ネパール」本学英会話講師 USHA MAHAT先生
第2部「世界の屋根 ヒマラヤ」35期生 北 敏和さん
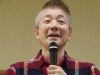
令和元年11月19日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「令和元年にふりかえる元号(年号)と日本人の歩み」

令和元年11月5日(火)
南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生「近未来─日本の可能性」⑤

令和元年10月29日(火)
公益財団法人角屋保存会理事長
中川清生 先生「京島原の歴史と文化」

令和元年10月15日(火)
泉佐野市長
千代松大耕 先生「ふるさと納税をめぐって」

令和元年10月1日(火)
朗読家・フリーアナウンサー
辻 ひろ子 先生「谷崎潤一郎の魅力」─お話と朗読─
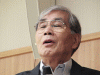
令和元年9月17日(火)
近畿大学名誉教授・水産研究所顧問
村田 修先生「近大マグロの増養殖」

令和元年9月10日(火)
毎日新聞学芸部専門編集委員
畑 律江 先生「大阪の古典芸能の今」

令和元年9月3日(火)
和歌山大学准教授
大橋直義 先生「『平家物語』と奈良」
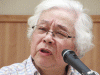
令和元年7月16日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生八木亜夫の「世相を斬る」

令和元年7月9日(火)
田中克彦と「イリマ アイランダース」「年は寄ってもハワイアン」
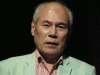
令和元年6月25日(火)
京都大学名誉教授 大石 眞 先生「鵜の目・鷹の目・まことの目」④
同夫人 大石悦子 先生「歌会始のこと」
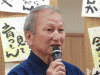
令和元年6月18日(火)
書工房 慶樹主宰
辻 慶樹 先生「どうする人生100年時代」─ プラスのことばは魔法のことば ─
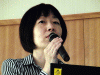
令和元年6月11日(火)
岸和田市立病院主任医療ソ-シャルワーカー
澤近敦子 先生 シリーズ講座「フレイル&サルコペニアの備え」①─ 病院の役割分化の現状について─

令和元年6月4日(火)
㈱自然総研主任研究員 荒武貞雄 先生「人生100年時代を生きるお金との向き合い方」
池田泉州銀行営業統括部 小関守弘 先生「自宅を活用した老後資金の作り方」

令和元年5月28日(火)
岸和田市長
永野耕平 先生「岸和田市政について」

令和元年5月21日(火)
大阪府立近つ飛鳥博物館名誉館長
白石太一郎 先生「百舌鳥・古市古墳群の語るもの」

令和元年5月14日(火)
大阪地方裁判所裁判官「裁判員制度」
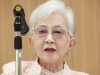
令和元年5月7日(火)
フリーアナウンサー
渡部淑子 先生「難病を克服して」

平成31年4月23日(火)
理事長 山田祥次 先生・(理事=内定)山田哲明 先生
「たいまつを受け継ぐ」

平成31年4月16日(火)
フレンズ・ウィズ・アウト・ア・ボーダー代表
赤尾和美 先生 特別記念講演「ラオスからの便り」

平成31年3月19日(火)
本学理事長
山田祥次 先生 修了記念講演
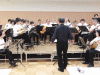
平成31年3月12日(火)
マンドリンアンサンブル「はるか」
三好貞夫さんら「ブラボー!!マンドリン」
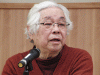
平成31年3月5日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成31年2月26日(火)
東京国際大学教授
阪口規純 先生「戦後日本と明仁天皇の平和主義」

平成31年2月16日(火)
耳ツボジュエリーアーティスト
小橋美栄子 先生「耳ツボを知っていますか」

平成31年2月12日(火)
産経新聞編集委員
石野伸子 先生「女性記者45年の置き土産」
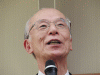
平成31年2月5日(火)
37期生(管理栄養士)
双和光雄 先生「健康寿命を延ばす食事管理」
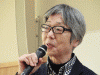
平成31年1月29日(火)
美術評論家
岩佐倫太郎 先生「お出かけ美術館」
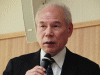
平成31年1月23日(水)
京都大学名誉教授
大石 眞 先生「鵜の目・鷹の目・まことの目」③~ 2019年の展望 ~

平成31年1月15日(火)
特別公演
堺シティオペラ理事長
坂口茉里 先生「オペラはいかが」

平成31年1月8日(火)
新春コンサート
コーラスクラブ講師 平松啓子 先生・ピアノ太田紀子 先生「世界の歌 日本の歌」
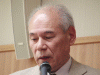
平成30年12月11日(火)
京都大学名誉教授
大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」②

平成30年12月4日(火)
泉佐野泉南医師会看護専門学校副学校長
西田好江 先生「看護学あれこれ」

平成30年11月22日(木)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成30年11月6日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「蛸蛸から漫才まで:タコの文化誌」

平成30年10月30日(火)
司馬遼太郎記念館館長
上村洋行 先生「司馬遼太郎の考えたこと」

平成30年10月23日(火)
桂山智哉さん&江上 昇さん
元漫才師公務員の「お笑い行政講座」
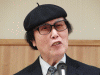
平成30年10月17日(水)
作家
難波利三 先生「てんのじ村と吉本興業」
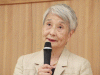
平成30年10月2日(火)
元「宝塚・アフガニスタン友好協会」代表
西垣敬子 先生「私のアフガニスタン」

平成30年9月18日(火)
和歌山大学准教授
大橋直義 先生「平清盛と西行」

平成30年9月11日(火)
桃山学院大学エクステンションカレッジ講師
檜本多加三 先生「だんじり祭総まくり」
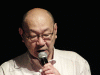
平成30年8月7日(火)市民公開講座③
森之宮病院心臓血管センター部長
大久保修和 先生「大動脈瘤治療の改革」-ステントグラフト治療-
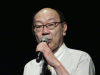
平成30年7月31日(火)市民公開講座②
森之宮病院心臓血管センター部長
大久保修和 先生「心臓血管外科の治療の進化」-冠動脈疾患・弁膜症手術など-
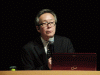
平成30年7月24日(火)市民公開講座①
関西大学法学部教授・同大学法学研究所長
久保宏之 先生 「家族の法の現在」-最近の最高裁判決と相続法改正-
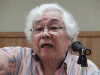
平成30年7月17日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成30年7月10日(火)
アンサンブル・レヴィオール
ヴィオラ・ダ・ガンバ橋詰玲子さん
リュート小出智子さん 「現代に生きるルネサンス音楽」

平成30年7月3日(火)
岸和田署交通課・生活安全課 生活・交通安全講習
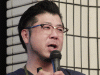
平成30年6月26日(火)
野花ヘルスプロモーター冨田昌秀 先生
にしだJクリニック西田純子 先生「“みまーも岸和田”参上!」

平成30年6月19日(火)
和歌山大学災害科学教育研究センター客員教授
マーケティング・プランナー
今西 武 先生「リアルな防災対策を」

平成30年5月29日(火)
歯科医&ラジオパーソナリティー
中井大介 先生「唾液は万病の薬」
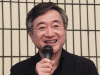
平成30年5月22日(火)
大阪健康福祉短期大学学長・小児科医
眞鍋 穣 先生「診察室から見える子どもの心と体…食物アレルギーにふれて」

平成30年5月15日(火)学生発表
35期生井上正己さん「受章とボランティア活動」
39期生 玉置福夫さん「初級・相続について」)」
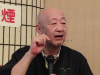
平成30年5月1日(火)
神戸大学教授
巽 好幸 先生「地震列島・火山列島の日本に暮らすということ」(下)」

平成30年5月1日(火)
神戸大学教授
巽 好幸 先生「地震列島・火山列島の日本に暮らすということ」(上)」
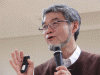
平成30年4月24日(火)
神戸大学教授
松岡広路 先生「持続可能な社会づくりに果たす私たちの役割」

平成30年4月17日(火)特別記念講演
京都大学名誉教授
大石 眞 先生「鵜の眼・鷹の眼・まことの眼」①

平成30年3月20日(火)修了記念講演
本学理事長
山田祥次 先生

平成30年3月13日(火)
さかい利晶の杜(与謝野晶子記念館)学芸員
森下明穂 先生 生誕140年記念「情熱の歌人・与謝野晶子」
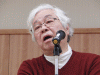
平成30年3月6日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成30年2月27日(火)
東京国際大学教授
阪口規純 先生「憲法9条と安全保障」

平成30年2月20日(火)
能楽師
勝部延和 先生「応仁の乱と能」(下)

平成30年2月13日(火)
毎日新聞元運動部長
玉置通夫 先生「センバツ90回の春」
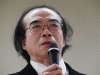
平成30年2月7日(水)
南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生「平成30年-昭和は遠くなりにけり」

平成30年1月30日(火)
羽衣国際大学教授
浮田 哲 先生「Fake Newsの波紋」
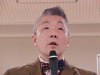
平成30年1月23日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「初春を寿ぐ海老のはなし」
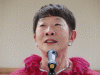
平成30年1月16日(火)
DAS総合デザイー協会会員
広瀬カヤ子 先生「70歳の青春」~ マスターズスイマーの挑戦 ~
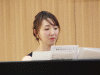
平成30年1月9日(火)
新春ほほえみコンサート
ソプラノ 柳内葵衣さん・バリトン 松澤政也さん・ピアノ 吉田衣里さん

平成29年12月12日(火)
NPO法人「遺族支え愛ネット」前代表・健康生きがいづくりアドバイザー
出口久美 先生「よりよく生きるために」
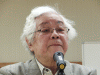
平成29年12月5日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生八木亜夫の「世相を斬る」

平成29年11月28日(火)
龍谷大学世界仏教文化研究センター博士研究員
唐澤太輔 先生 生誕150年によせて「巨人・南方熊楠の実像」

平成29年11月21日(火)
大阪国際大学客員教授
阪口葉子 先生「おもてなし観光」
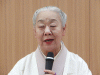
平成29年11月7日(火)
橘流日本橘会大師範・重要無形文化財保持者(人間国宝)
奥村旭翠 先生「筑前琵琶への誘い」

平成29年10月31日(火)
京都国立博物館学芸部長
山本英男 先生「『国宝』展の魅力」

平成29年10月24日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「にっぽん大泥棒ものがたり」

平成29年10月17日(火)
産経新聞編集委員
石野伸子 先生「浪花の女傑再発見」
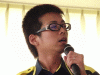
平成29年10月3日(火)
岸和田市危機管理課 甲地将史 先生「災害時の心構え」
消防本部予防課参事 小幡 昇 先生「災害心理について」

平成29年9月19日(火)
和歌山大学准教授
大橋直義 先生「平家物語と熊野」
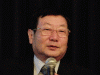
平成29年9月12日(火)
美術評論家・毎日新聞元専門編集委員
田原由紀雄 先生「日本史を書きかえた飛鳥美人~その光と影~」

平成29年9月5日(火)
国際総合研究所代表
中島英迪 先生「退位と譲位のはざ間」~新皇室像をめぐって~

平成29年8月8日(火)
夏季公開講座③「日本国憲法の今日と明日」~デモクラシーのかたち~
大阪大学准教授 片桐 直人 先生

平成29年8月1日(火)
夏季公開講座②施行70年「日本国憲法の今日と明日」
近畿大学教授 上田 健介 先生
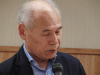
平成29年7月25日(火)
夏季公開講座①施行70年「日本国憲法の今日と明日」
京都大学名誉教授 大石 眞 先生
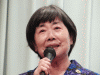
平成29年7月11日(火)
市民公開講座
岸和田・北町だんじり劇場館長
久場共見子 先生「だんじり女一代」~つよく やさしく しなやかに~
市民公開講座・仏教特別講話
僧侶・著述家
草薙龍瞬 先生「心のお通じ」に抜群の効果!~ 仏教式・お悩みスッキリ解消術 ~

平成29年6月27日(火)
本学講師
店田全弘 先生 没後150年「今に生きる坂本龍馬」

平成29年6月20日(火)
社会福祉法人五風会理事長
土金新治 先生「どうなる、どうするこれからの日本の保育」

平成29年6月13日(火)
本学短歌クラブ講師
鈴木きぬ子 先生「正岡子規の周辺」
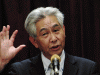
平成29年6月6日(火)
岸和田警察署交通総務課
米田 孝 警部補 交通安全講習

平成29年5月30日(火)
野村證券岸和田支店ファイナンシャル・アドバイザー
行松浩司 先生「トランプ相場を読む」
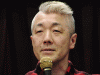
平成29年5月23日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「蟹づくしの結末やいかに:蟹と日本文化」

平成29年5月16日(火)
龍谷大学名誉教授
木坂順一郎 先生「田中角栄の光と影」(下)

平成29年5月9日(火)
龍谷大学名誉教授
木坂順一郎 先生「田中角栄の光と影」(中)

平成29年5月2日(火)
龍谷大学名誉教授
木坂順一郎 先生「田中角栄の光と影」(上)~吉田茂・池田勇人を超えて~)
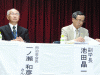
平成29年4月25日(火)
フォーラム「健老のかたち」18期生 太田重雄さん・30期生 古江常太郎さん・一ノ瀬和彦学生自治会会長・池田晶一 副学長 (司会 鶴田隆志)

平成29年4月18日(火)
特別記念講演
大阪城天守閣館長
北川 央 先生「大坂の陣後日談」

平成29年3月21日(火)
本学理事長 山田祥次 先生 修了記念講演

平成29年3月14日(火)
京都大学教授
奈良岡聰智 先生「岡部長景」─ある華族政治家の軌跡─

平成29年3月7日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生八木亜夫の「世相を斬る」
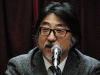
平成29年2月28日(火)
東京国際大学教授
阪口規純 先生「米国トランプ新政権と日本の安全保障」

平成29年2月21日(火)
和泉市久保惣記念美術館学芸員
後藤健一郎 先生「泉州の宝庫」─地元に眠る名品の数々─

平成29年2月14日(火)
本学講師
髙橋純子 先生「日本とカナダの懸け橋に」~髙橋純子の挑戦~

平成29年2月7日(火)
「救犬ジャパン」理事長
松林良子 先生「頼もしい救助犬」

平成29年1月31日(火)
のばな訪問看護ステーション管理者
冨田昌秀 先生「認知症の人の気持ち」~思いを理解して関わる~

平成29年1月24日(火)
本学講師
永田之子 先生「コミュニケーションナビ」

平成29年1月17日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「龍と海女珠取伝説」

平成29年1月10日(火)
新春コンサート「ニコニコニ胡」
39期生 片山芳子さんら
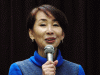
平成28年12月13日(火)
生命の貯蓄体操普及本部理事長
矢野順子 先生「今こそ求められる東洋医学」

平成28年12月6日(火)
学生発表「介護保険あれこれ」
27期生 山本一美 さん
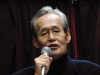
平成28年11月29日(火)
毎日新聞大阪本社元編集局次長
吉田嘉彦 先生「人生模様─じじい爺の哀歌」」
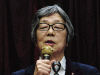
平成28年11月22日(火)
美術評論家・美術ソムリエ
岩佐倫太郎 先生 楽しさ倍増!!「絵の見方・美術館のまわり方」」

平成28年11月15日(火)
マンドリン・アンサンブル「はるか」代表
三好貞夫さんら「マンドリンは招く」

平成28年11月1日(火)
文芸評論家
倉橋健一 先生「関西の夏目漱石」」
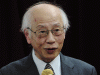
平成28年10月25日(火)
立命館大学非常勤講師
保井 温 先生「本居宣長からみた源氏物語」

平成28年10月18日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
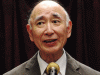
平成28年10月4日(火)
高野山霊宝館副館長・高野山大学名誉教授
山陰加春夫 先生「平家物語と高野山」

平成28年9月13日(火)
和歌山大学准教授
大橋直義 先生「文覚の恋=『平家物語』と室町物語」

平成28年9月6日(火)
関西大学法学部教授
山野博史 先生「発掘 司馬遼太郎」
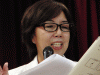
平成28年8月9日(火)夏季公開講座③
全日本らくらくピアノ協会大阪支部2級認定講師
古曵知子 先生ら(岩田瑞代先生 上野玲子先生)「ピアノ弾きませんか」

平成28年8月2日(火)夏季公開講座②
毎日新聞大阪本社元運動部長
玉置 通夫 先生「リオデジャネイロからT0KYOへ」~ オリンピックの展望と課題 ~

平成28年7月26日(火)夏季公開講座①
京都大学防災研究所地震予知研究センター准教授・博士
西村卓也 先生「熊本地震の発生メカニズムと南海トラフ地震」

平成28年7月19日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成28年7月12日(火)
帝塚山学院大学生涯学習センター講師
八木孝昌 先生「万葉集の概要」

平成28年6月28日(火)学生発表
①「私と走り」鈴木克爾さん(35期)
②「地域社会と共に」平田勝巳さん(28期)

平成28年6月21日(火)
岸和田徳洲会病院臨床検査科副技師長
林 光久 先生「血液検査の見方について」
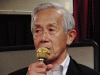
平成28年6月14日(火)
NPO法人TMC会員
芳木通泰 先生「鐵よもやま話」

平成28年6月7日(火)
岸和田警察署交通総務課
米田 孝 警部補 交通安全講習

平成28年5月31日(火)
上方文化評論家 福井栄一 先生
「目を見張る 目のはなし~目と日本文化」

平成28年5月24日(火)
歴史研究サークル南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生「『近現代史をひもとく』の締めくくりに」

平成28年5月17日(火)
産経新聞元台北支局長
吉村剛史 先生「どうなる台湾、民進党政権~いよいよ蔡英文新総統が就任」
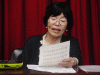
平成28年4月26日(火)
「心のうた・健老のうた」
指導 乕田良子 先生と「心のうたをうたいましょう」グループ

平成28年4月19日(火)
奈良大学教授
上野 誠 先生「万葉びとの生活」

平成28年3月15日(火)
本学理事長
山田祥次先生 修了記念講演

平成28年3月8日(火)
学生発表「自分史を語る」
山田勝子さん(32期)
中大路芳一さん(21期)

平成28年3月1日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成28年2月23日(火)
日本学協会関西支部事務局長
野崎眞夫 先生「日本学入門」

平成28年2月16日(火)
本学副学長
池田晶一 先生「真田幸村の郷・九度山」

平成28年2月9日(火)
サイクル・トレイン旅企画
田中貞夫 先生「旅することは生きること」

平成28年2月2日(火)
和歌山大学教育学部准教授
大橋直義 先生「『平家物語』を読むということ~ 概論として」

平成28年1月26日(火)
毎日新聞編集委員
中西 満 先生「経済記者から見た社会動向」

平成28年1月19日(火)
帝塚山学院大学 名誉教授
鶴崎裕雄 先生「大坂夏の陣・落人の行方」

平成28年1月12日(火)
松下政経塾元塾頭・「志」 ネットワーク代表
上甲 晃 先生「人生に無駄な経験などない」
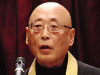
平成27年12月8日(火)
浄土宗安福寺住職
伊藤正哲 先生「人生のたそがれを美しく」

平成27年12月1日(火)
モラロジー研究所教授・京都産業大学名誉教授
所 功 先生「『昭和天皇実録』に学ぶ高齢者の生き方」

平成27年11月24日(火)
NPO法人「下水道と水環境を考える会・水澄」理事・市民講座部会長
小沢和夫 先生「水環境の担い手・下水道を知る」
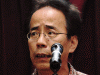
平成27年11月10日(火)
mottoひょうご事務局長
栗木 剛 先生「いまどきの高齢者」
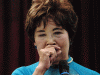
平成27年10月27日(火)
奈良大学元講師
向野幾世 先生「絆」
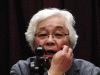
平成27年10月20日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
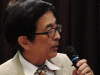
平成27年10月6日(火)
子規研究家・作庭家
正岡 明 先生「正岡子規の周辺」

平成27年9月15日(火)
野村證券証券学習開発課 須長忠男 先生
岸和田支店 行松浩司 先生「どうなる年金・これからの将来」

平成27年9月8日(火)
パナソニック㈱エコソリューションズ社エイジフリーBU主幹
志方宣之 先生「よりそう ささえるロボット」
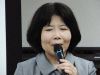
平成27年9月1日(火)特別記念講演
ACグループカウンセラー
白井好子先生 「カウンセリングマインド」~心の声を聴く~
監修 山田祥次 先生

平成27年8月25日(火)夏季公開講座③
東京国際大学国際関係学部教授
阪口規純 先生「戦後70年日本の平和を考える」~憲法と日米安保の狭間で~

平成27年8月4日(火)夏季公開講座②
座談会「昭和1けたの覚悟」
16期生降旗忠良さん 13期生水野ヒデさん 28期生坊農喜代治さん 18期生松阪喜代治さん 18期生太田重雄さん 35期生楠部治さん 14期生藪道子さん 19期生内田幸子さん 25期生中西久忍夫さん
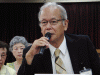
平成27年7月28日(火)夏季公開講座①
座談会「大正世代の底力」
22期生岡田哲夫さん 31期生山田トキさん 9期生角谷芳雄さん 17期生古賀玉彦さん

平成27年7月21日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成27年7月14日(火)
関西医療大学はり灸・スポーツトレーナー学科准教授
坂口俊二 先生「きょうから使えるツボの話」

平成27年6月30日(火)
歴史研究サークル南木倶楽部全国代表
南木隆治 先生 戦後70年「近現代史をひもとく」①

平成27年6月23日(火)
日本野鳥の会男里川探鳥会リーダー
中田 亘 先生「野鳥に魅せられて
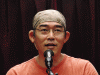
平成27年6月16日(火)
芥川賞作家
吉村萬壱 先生「高齢者の文学」

平成27年6月9日(火)
重要無形文化財[総合]能楽師
勝部延和 先生「能の魅力」~道成寺~
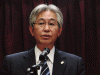
平成27年6月2日(火)
岸和田警察署交通課
米田 孝 警部補 生活安全講習 交通事故防止と特殊詐欺
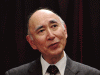
平成27年5月26日(火)
高野山大学名誉教授
山陰加春夫 先生 高野山開創1200年記念「高野山の歴史と信仰」

平成27年5月19日(火)
本学副学長
池田晶一 先生 大坂夏の陣400年「真田丸を行く」

平成27年5月12日(火)
ゲームソフト会社「ユークス」社長
谷口行規 先生「企業家レーサーの疾走!!」
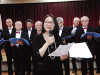
平成27年4月28日(火)
38期生歓迎ジョイントコンサート
コーラスクラブ・ボーカルクラブ

平成27年4月21日(火)特別記念講演
雑誌『上方芸能』発行人
木津川 計 先生「生き甲斐のこれから」

平成27年3月17日(火)
本学理事長
山田祥次 先生 修了記念講演
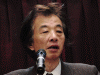
平成27年3月10日(火)
毎日新聞大阪本社元G3部長
木田智里 先生「新聞記者が見た東日本大震災」~3.11から4年故郷を想い考える~

平成27年3月3日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成27年2月24日(火)
羽衣国際大学現代社会学部教授
泉 紀子 先生「伊勢物語から源氏物語へ」
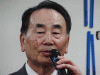
平成27年2月17日(火)
ライオンズ国際協会335-B地区第1副ガバナー
中村 猛 先生 シニアの皆さんへ「社会への恩返しの心で頑張ろう」
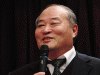
平成27年2月10日(火)
ミキ・ブレインズ電子出版局
実城良一 先生「自分で出来る電子図書出版」
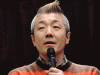
平成27年2月3日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「誰もが気になる髪のはなし」

平成27年1月27日(火)
武蔵野大学環境学部教授
一方井誠治 先生「環境経済学の発想(原点)」
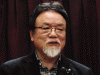
平成27年1月20日(火)
喜多クリニック院長 喜多 薫 先生「腰痛よさようなら」

平成27年1月13日(火)
水間鉄道会長
関西佳子 先生「女性として企業経営者として」

平成27年1月6日(火)
新春コンサート~愛と花にあふれて~
ソプラノ 花篤孝子先生
ピアノ 道下佳世 先生

平成26年12月9日(火)
理事長 山田祥次
学 長 鶴田隆志
「健老40年に向けて」~理事長&学長対談~

平成26年12月2日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成26年11月18日(火)
岸和田徳洲会病院検診センター長
畠山勝二 先生「生活習慣病について」
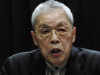
平成26年11月4日(火)
文芸評論家
倉橋健一 先生「読書のウラオモテ」
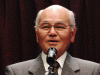
平成26年10月28日(火)
【学生発表】 32期生 水野和夫さん「運営委員を務めて」
【映像による発表会】 ①ノルディックウオーキング・②囲碁・③ペンギンゴルフ・④水泳
【学生発表】 35期生 井上正己さん「語学研修の旅」

平成26年10月21日(火)
医療法人気象会東朋病院医師
桑島士郎 先生「目からウロコの生命科学」

平成26年10月7日(火)
大阪大学人間科学研究科准教授
権藤恭之 先生「老年行動学入門」
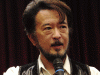
平成26年9月16日(火)
ミュージシャン
渡部勝喜 先生「アンデス音楽の魔術師」

平成26年9月9日(火)
日本体育協会公認上級指導員
清水幸恵 先生「こんな坂みんなで越えよう」~簡単体操でしなやかに~

平成26年9月2日(火)
日本体育大学理事長日本アフガニスタン協会理事長
松浪健四郎 先生 特別記念講演「イスラム教の国々」
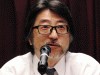
平成26年8月5日(火)夏季公開講座③
東京国際大学国際関係学部教授
阪口規純 先生 東アジア情勢と日本の安全保障 ~第1次世界大戦後100年の節目に~

平成26年7月29日(火)夏季公開講座②
大阪市立大学大学院 特任教授
川上三郎 先生 ―宇宙の始まりから現在まで―

平成26年7月22日(火)夏季公開講座①
毎日新聞大阪本社元運動部長
玉置 通夫 先生「高校野球100年目の夏」
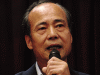
平成26年7月15日(火)
木山財務コンサルタント事務所代表
木山順三 先生「知っておきたい遺産相続」

平成26年7月1日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成26年6月24日(火)
岸和田市消防本部消防長
貝塚谷光一 先生「地域防災力を高める」
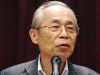
平成26年6月17日(火)
新風書房社長
福山琢磨 先生「自分史のすゝめ」
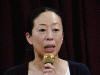
平成26年6月10日(火)
女 優 林 英世 先生
「表現する楽しさ~こえことばの世界~」─ひとり語り・太宰 治「葉桜と魔笛」&ワークショップ ─
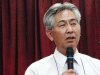
平成26年6月3日(火)
岸和田警察署交通課 米田 孝 警部補
交通安全講習

平成26年5月27日(火)
大阪観光大学准教授 崎本武志 先生
「鉄路はつづく」~オリエント急行からななつ星まで~

平成26年5月20日(火)
池田泉州銀行
常務 野田 隆 先生
副部長 近藤圭一郎 先生「アベノミクスと消費税増税」

平成26年5月13日(火)
紀三井寺副住職 前田泰道 先生 「仏教といやし」
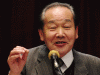
平成26年4月22日(火)
本学講師小山 昇 先生
古典への招待62「枕草子と藤原一族」

平成26年4月15日(火)
日本安全保障・危機管理学会顧問日本経済大学大学院特任教授 矢野義昭 先生
特別記念講演「緊迫する北東アジア情勢─何が動かし、どこへ向かおうとしているのか─」

平成26年3月18日(火)
本学理事長 山田祥次 先生 修了記念講演

平成26年3月11日(火)
和歌山大学防災研究教育センター客員教授
今西 武 先生「私たちは『3・11』を忘れない」

平成26年3月4日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
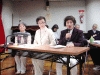
平成26年2月25日(火)
学生発表
①「伊勢神宮式年遷宮に参加して」31期生 西田和子さん 33期生 松阪ナツ子さん 35期生 田野晴子さん
②「異文化との付き合い方」34期生 米子明義さん

平成26年2月18日(火)
毎日新聞編集委員
西村浩一 先生 「世界遺産・富士を語る」

平成26年2月4日(火)
アナウンサー・古典芸能解説者
葛西聖司 先生「こいつは春から縁起がいいわ」~歌舞伎の力~

平成26年1月28日(火)
料理研究家
程 一彦 先生「健康を食べる食事学」~ 日本料理と中国料理で元気に ~

平成26年1月21日(火)
フリーアナウンサー
渡部淑子 先生「美しい日本語」
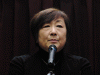
平成26年1月14日(火)
女優・ベルばら初代オスカル
榛名由梨 先生 宝塚歌劇100年「タカラヅカ歌語り」

平成26年1月7日(火)
新春コンサート「世界の歌・日本の歌」
本学講師 平松啓子 先生 ピアノ伴奏 太田紀子 先生

平成25年12月10日(火)
大阪城天守閣研究主幹
北川 央 先生「熊野街道をめぐる物語と信仰」
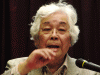
平成25年12月3日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成25年11月26日(火)
長尾クリニック院長
長尾和宏 先生「平穏死・10の条件」

平成25年11月19日(火)
生命の貯蓄体操普及会理事長
矢野順子 先生「養生について」─ 生命の貯蓄 ─
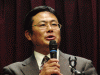
平成25年11月5日(火)
浄土真宗親鸞会布教師
山中 徹 先生「親鸞聖人の教え」
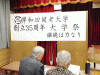
平成25年10月29日(火)
大学祭月間・映像発表会「継続は力なり」
水泳・ペンギンゴルフ・囲碁・ノルディックウオーキング 各クラブ

平成25年10月22日(火)
拓殖大学客員教授
惠 隆之介先生「沖縄はいま」

平成25年10月8日(火)
天理大学名誉教授
村上嘉英 先生「台湾の言葉と文化」

平成25年10月1日(火)
和歌山大学防災研究教育センター客員教授
今西 武 先生「リアルな防災対策」

平成25年9月17日(火)
学長 鶴田隆志「サバイバル10」~22・67・80目指し~

平成25年9月10日(火)
三田市吹奏楽連盟会長・縦笛の魔術師
梶谷正治 先生「笑って歌って笛聴いて心さわやか 良い気分!!」

平成25年9月3日(火)
写真家・大阪芸術大学非常勤講師
宮田昌彦 先生「カメラが見た『岸和田旧市だんじり祭』」

平成25年8月6日(火)夏季公開講座③
東京国際大学国際関係学部教授
阪口規純 先生「憲法改正問題を考える」
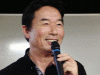
平成25年7月30日(火)夏季公開講座②
岸和田市立光陽中学校校長
堂本啓祐 先生「民間人中学校長の現場からの報告」

平成25年7月23日(火)夏期公開講座①
トルコ航空旅客サービス
ユルドゥルム・ファーティ 先生「トルコと日本~文化の違い」

平成25年7月16日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
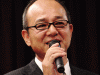
平成25年7月9日(火)
料亭 はんなり経営
松阪義典 先生「おもてなしの心」
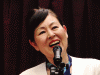
平成25年6月25日(火)
ユナイテッド航空関西国際空港支店長
阪口葉子 先生 「世界の空と日本の空」
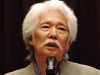
平成25年6月18日(火)
シニアライフ研究家
中村 義 先生 「エッセイを楽しもう」
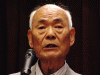
平成25年6月11日(火)
大阪府地球温暖化防止活動推進員
奥 清司 先生「泉州から地球温暖化を考える」

平成25年6月4日(火)
岸和田警察署
交通安全教育

平成25年5月28日(火)
本学短歌クラブ講師
鈴木きぬ子 先生「高齢者の詠む短歌」

平成25年5月21日(火)
本学OB
小林太一 先生 「91歳・ボランティア三昧」

平成25年5月14日(火)
兵庫県立大学教授
石倉和佳 先生 「徳冨蘇峰と新島八重」

平成25年5月7日(火)
大阪大学大学院教授
阿部武司 先生「泉州における繊維産業の盛衰」─東洋のマンチェスターの周辺─
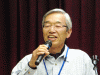
平成25年4月30日(火)
本学35期生
北 敏和 さん 学生発表「日本百名山を踏破して」

平成25年4月23日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「古事記物語」~なにわのことは夢のまた夢~

平成25年4月16日(火)
特別記念講演
毎日新聞社論説副委員長
近藤伸二 先生「危機に立つ日本のものづくりと台頭するアジア企業」

平成25年3月19日(火)
修了記念講演
本学理事長
山田祥次 先生

平成25年3月12日(火)
弁護士
相馬達雄 先生「エンディング法律相談」

平成25年3月5日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
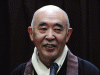
平成25年2月26日(火)
宝樹寺住職
土井歓晃 先生 法話「水心力」

平成25年2月19日(火)
「大阪アスベスト弁護団」弁護士
西本哲也 先生「泉南アスベスト訴訟の今」
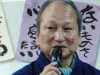
平成25年2月12日(火)
「ことば&書」創人
辻 慶樹 先生「プラスのことばは魔法のことば」

平成25年2月5日(火)
フロンティアエイジ元編集長
朝日新聞元記者
向平すすむ 先生コミュニティーハウス法隆寺「小さな共生の住まい」
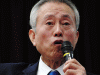
平成25年1月29日(火)
枚岡神社宮司 中東 弘 先生「神道と元氣蘇生」

平成25年1月22日(火)
日本ペンクラブ会員・毎日新聞元編集委員
田原由紀雄 先生「京都宗教界と作家たち」~宗教記者35年の取材ノートから~

平成25年1月15日(火)
本学川柳講師
吉道航太郎 先生「笑って川柳」

平成25年1月8日(火)
新春クラシックコンサート
「フルート・ヴァイオリン・ピアノの調べ」
田尻トリオ 豊田真理(フルート)、石田知子(ヴァイオリン)、脇 由美子(ピアノ)
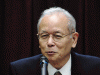
平成24年12月11日(火)
学長
鶴田隆志 先生 「健老大学の大正人」
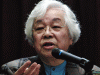
平成24年12月4日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
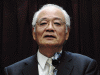
平成24年11月27日(火)
(財)災害科学研究所理事長・大阪大学名誉教授
松井 保 先生 「地球と地盤の中をのぞいてみよう」

平成24年11月20日(火)
(社)福祥福祉会理事運営本部長
阿久根 賢一 先生 「超高齢社会に咲く豊泉家(ほうせんか)」

平成24年11月6日(火)
俳優・シニア劇団「すずしろ」指導
倉田 操 先生「晴れ舞台はブロードウェイで!」
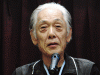
平成24年10月30日(火)
学生発表
①31期生・運営委員 服部武志 さん「癒しの音楽」
②34期生 井ノ口 宏 さん「世界100ヶ国巡り」

平成24年10月23日(火)
高砂大学校同窓会のみなさん「金沢・高砂大学校同窓会アワー」

平成24年10月9日(火)
伊勢神宮評議員・伊勢市観光協会会長
山中隆雄 先生「お伊勢さんの式年遷宮」

平成24年10月2日(火)
泉佐野市長
千代松大耕 先生「アイデア市長奮闘記」
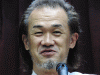
平成24年9月25日(火)
岸和田徳州会病院顎顔面口腔外科部長
岩田雅裕 先生「カンボジアでの医療支援」

平成24年9月18日(火)
毎日新聞論説委員
藤田 悟 先生「ミャンマーとビルマ」

平成24年9月11日(火)
グループホーム「つぼみ」施設長
奥 幸博 先生「終の住処としてのグループホーム」

平成24年9月4日(火)
大阪府立大学教授
清水教永 先生 「わがままな体内時計が健康長寿のもと」
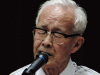
平成24年8月7日(火) 夏季公開講座③
毎日新聞元記者・中外日報前論説委員
山野上純夫 先生 「原発問題とヒロシマ」
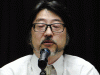
平成24年7月31日(火) 夏季公開講座②
東京国際大学国際関係学部教授
阪口規純 先生 「北朝鮮核開発問題と戦後日本の核政策」
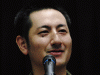
平成24年7月24日(火) 夏季公開講座①
浄土宗西光寺住職
寺尾昌治 先生 三味線法話「仏教と三味線の不思議なご縁」
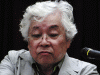
平成24年7月17日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
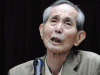
平成24年7月10日(火)
本学講師
浜田禎三 先生「米寿からの挑戦」
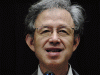
平成24年6月26日(火)
地震考古学者
寒川 旭 先生「地震考古学入門」

平成24年6月12日(火)
国際女医会前会長・埼玉医大名誉教授
平敷淳子 先生「国際女医会長のたどった世界」
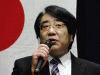
平成24年6月5日(火)
防犯教育
岸和田警察署・生活安全課
「振り込めサギに引っ掛からないために」
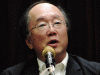
平成24年5月29日(火)
サイクリスト
田中貞夫 先生「ドイツ・ロマンチック街道自転車旅」

平成24年5月22日(火)
元岸和田藩主・岡部家16代
三重県・城田神社元宮司
岡部長禮 先生「岸和田だんじり祭と岡部家」

平成24年5月15日(火)
大正紡績取締役
近藤健一 先生「オーガニックコットン」
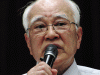
平成24年5月8日(火)
「獅林」編集長
森 一心先生「俳句を楽しむ」

平成24年5月1日(火)
本学講師 小山 昇 先生 古典ヘの招待48
「平清盛─時代を変えた男─」
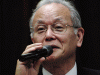
平成24年4月24日(火)
学長 鶴田隆志 先生
「『舟』を読もう」
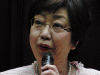
平成24年4月17日(火)
特別記念講演
元大阪府知事 太田房江 先生
「人生リセット論」─官僚・初の女性知事・事業家・NPO法人─
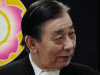
平成24年3月27日(火)
本学理事長
山田祥次 先生 修了記念講演

平成24年3月13日(火)
日本ノルディックウォーク協会理事・公認マスター
伊藤義昭 先生 「ノルディックウォーク体験」
協力・フロンティアエイジ
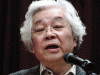
平成24年3月6日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫先生 八木亜夫の「世相を斬る」
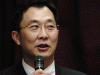
平成24年2月28日(火)
(株)北海製作所社長
林 孝彦 先生 「鉄人28号の夢をかたちに」

平成24年2月21日(火)
がんこフードサービス会長
小嶋淳司 先生 「がんこ一代」

平成24年2月14日(火)
NHK連続テレビ小説「カーネーション」チーフ・プロデューサー
城谷厚司 先生 NHK朝ドラ「『カーネーション』を語る」~その人気と反応~

平成24年2月7日(火)
本学英会話クラブ講師
髙橋純子 先生「異文化おもしろ発見」

平成24年1月31日(火)
KSC鳳スイミングスクール
葉室三千子 先生・広瀬カヤ子先生
「92歳&64歳親子女性スイマーの夢」
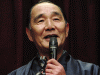
平成24年1月24日(火)
能楽師・大倉流大鼓方
辻 芳昭 先生「能楽のすべて」~鼓に触ろう~
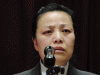
平成24年1月17日(火)
Y&S代表取締役
竹内洋子 先生・竹内園絵 先生「阪神淡路大震災から17年」
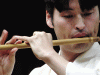
平成24年1月10日(火)
「民の謡」代表取締役 森田 玲 先生
「民の謡」岸和田店店長 城 かおり 先生 和楽演奏会「篠笛の調べ」

平成23年12月13日(火)
建築家
吉野富博 先生「地震に強い家の話」
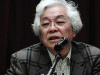
平成23年12月6日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成23年11月29日(火)
朗読アナウンサー
辻 ひろ子 先生「朗読・読み語りの世界」~美しい日本語を声で味わうために~
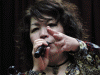
平成23年11月22日(火)
NPO法人「デセオ」代表理事
安田依央 先生「終活ファッションショーの贈り物」

平成23年11月15日(火)
龍谷大学教授
松島泰勝 先生「琉球自治共和国の可能性」
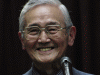
平成23年11月1日(火)
日本ユースホステル協会会員・技術士
間中俊夫 先生「欧州巡礼道を歩く」
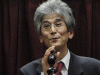
平成23年10月25日(火)
本学講師
井上信男 先生「ヨーガで健康に」
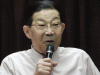
平成23年10月18日(火)
大阪教育大監事
野口克海 先生「子育て・孫育てPrat2」
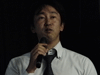
平成23年10月4日(火)
滋賀医科大学睡眠学教室 特任助教
北村拓朗 先生 「高齢者のための睡眠学」

平成23年9月27日(火)
与謝野晶子文芸館学芸員
森下明穂 先生 「与謝野晶子の魅力」─生涯と作品を通して─

平成23年9月20日(火)
上方文化評論家
福井栄一 先生「秋の草花の文化史」
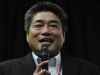
平成23年9月13日(火)
南大阪ヤクルト販売次長・健康管理士一般指導員
秋山真之 先生 「食中毒とその予防」

平成23年9月6日(火)
岸和田市危機管理室 岸和田市消防本部 岸和田市社会福祉協議会(協力)
「備えあれば・・・」─防災を考える─
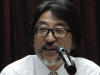
平成23年8月30日(火)
夏季公開講座 東日本大震災に学ぶ③
東京国際大学国際関係学部教授
阪口規純 先生 「東日本大震災・原発危機と安全保障」
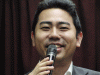
平成23年8月2日(火)
夏季公開講座 東日本大震災に学ぶ②
甲南大学マネジメント創造学部講師
林 万平先生 「東日本大震災の経済被害の迅速な推定と復興のあり方」
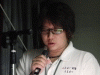
平成23年7月26日(火)
夏季公開講座 東日本大震災に学ぶ①
「東日本大震災被災地からの報告」
岸和田市社会福祉協議会職員 三林達哉さん 上松祐太さん
岸和田市青年団協議会会長 吉野保史さん
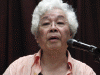
平成23年7月19日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
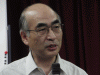
平成23年7月12日(火)
不二製油フードサイエンス研究所副所長
高松清治 先生 「健康食品とのつき合い方」
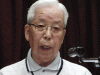
平成23年6月28日(火)
インターネットクラブ代表
野々村信郎 さん「IT社会で高齢者が生き抜くために」

平成23年6月21日(火)
岸和田市民病院地域医療センター副室長・ケースワーカー
和田光徳 先生 「地域の医療と介護」
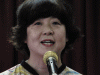
平成23年6月14日(火)
ふたば楽器会長 加藤正治 先生
オルガン奏者 花井 淑 先生 「懐かしのオルガンは今」

平成23年6月7日(火)
交通安全教育 岸和田警察署

平成23年5月31日(火)
植村牧場代表取締役
黒瀬礼子 先生 「共に働き共に生きる」─小さな町の牧童たち─
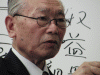
平成23年5月24日(火)
関西フィルハーモニー元代表
大川真一郎 先生 「私の夢・オペラハウス」
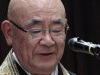
平成23年5月17日(火)
亀光庵庵主・前教化部長
土口哲光 先生 「お前はお前で丁度よい」
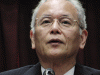
平成23年5月10日(火)
学長
鶴田隆志 先生 「心にひびく言葉」─名言ブームを探る─
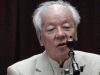
平成23年4月26日(火) 特別記念講演
日本画家
上村淳之 先生 「花鳥画に見る日本の美と心」
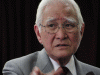
平成23年4月19日(火)
日本スマイリスト協会会長
近藤友二 先生「元気で長生き これが一番」
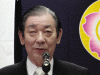
平成23年3月15日(火)
本学理事長
山田祥次 先生 修了記念講演

平成23年3月8日(火)
堺市立泉北すえむら資料館・関西学院大非常勤講師
森村健一 先生「世界遺産をめざす仁徳陵古墳と倭の五王の謎」
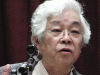
平成23年3月1日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成23年2月22日(火)
金沢大学名誉教授
永野耐造 先生「法医学実務のいろいろ」

平成23年2月15日(火)
出水クリニック院長
出水 明 先生「在宅で過ごすという選択肢─在宅ケアの現場から」
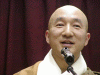
平成23年2月8日(火)
総本山知恩院布教師・正覚寺住職
阪口祐彦 先生 「法然上人と現代」

平成23年2月1日(火)
大阪教育大学常任監事
野口克海 先生 「子育て・孫育て・曾孫育て」
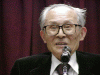
平成23年1月25日(火)
四天王寺大学名誉教授・船場大阪を語る会会長
三島佑一 先生 「大阪オーラと健老オーラ」

平成23年1月18日(火)
大阪市立科学館学芸員
飯山青海 先生 「小惑星『はやぶさ』7年の旅を振り返る」

平成23年1月11日(火)
オープニングコンサート「春の光と風」
楽団プロムナード主宰 中西治生 先生
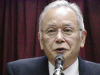
平成22年12月14日(火)
学長
鶴田隆志 先生「『坂の上の雲』の時代」
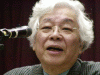
平成22年12月7日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
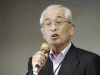
平成22年11月30日(火) 学生発表
①「上海万博見て歩き」 32期 木村好雄さん 田端信行さん
②「地下鉄建設物語」 30期 葛野恒夫さん

平成22年11月16日(火)
社会福祉法人「きらくえん」理事長
市川禮子 先生 「長寿社会の高齢者福祉」

平成22年11月2日(火)
奈良工業高等専門学校教授
松井良明 先生「スポーツ学のすすめ」
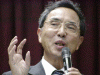
平成22年10月26日(火)
日本国際地図学会員
池田晶一 先生 「地図を楽しむ」

平成22年10月19日(火)
ヒグチ歯科グループCEO
樋口真弘 先生 「アクティブシニアを目指して」
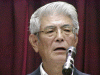
平成22年10月5日(火)
関西経済同友会安全保障委員会副委員長
田中克彦 先生「日本の安全保障」

平成22年9月28日(火)
宮大工棟梁
瀧川昭雄 先生「宮大工から見た古建築」
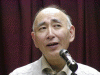
平成22年9月21日(火)
高野山大学元教授
山陰加春夫 先生「高野の聖たち」

平成22年9月14日(火)
理事長
山田祥次 先生「老化を科学する」
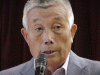
平成22年9月7日(火)
特別記念講演
プロゴルファー
杉原輝雄 先生 「生涯現役だ」
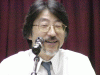
平成22年8月24日(火)
夏季公開講座 新しい風・変化の息吹③
東京国際大学教授
阪口規純 先生「普天間移設問題を論ず」
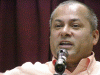
平成22年8月3日(火)
夏季公開講座 新しい風・変化の息吹②
インド日本友の会理事長
クンナ・ダッシュ 先生「インドを知ろう」~その食文化を通して~
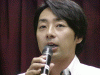
平成22年7月27日(火)
夏期公開講座 新しい風・変化の息吹①
大阪府立和泉高校校長
中原 徹 先生「グローバル社会を生き抜く教育とは」

平成22年7月20日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成22年7月13日(火)
本学講師
今口正一 先生「ロボットはお友達」

平成22年7月6日(火)
ペルシャ文化伝道士
ダリア・アナビアン 先生「関西とペルシャの赤いリボン」~文化と気質は従兄同士~

平成22年6月29日(火)
泉大津市立病院院長
永井祐吾 先生「身体にやさしい外科手術」─腹腔鏡下手術の紹介─

平成22年6月22日(火)
公証人
浦 文計 先生「安心して老後を過ごすために」─尊厳死・任意後見・遺言について─

平成22年6月15日(火)
毎日新聞客員編集委員
岡本健一 先生「平城京の光と影」
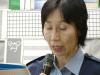
平成22年6月1日(火)
岸和田警察署 交通安全教育

平成22年5月25日(火)
西国29番札所 松尾寺住職
松尾心空 先生「人生の達人」

平成22年5月18日(火)
「健老大学の原点をたどる」~正井尚夫元学長の思い出~
理事長 山田祥次 先生・本学講師 浜田禎三 先生・本学元講師小林太一 先生

平成22年5月11日(火)
食品生成コンサルタント
殿元正徳 先生「健老を維持するための食の安全」

平成22年4月27日(火)
本学講師
小山 昇 先生 古典への招待34「平城遷都1300年に寄せて」-万葉秀歌ものがたり-

特別記念講演・同窓会員招待
平成22年4月20日(火)
家族会元代表
横田 滋さん
横田 早紀江さん 「拉致被害者をかえして」~娘・めぐみさんを想う横田 滋・早紀江さんの叫び~

平成22年3月16日(火)
本学理事長
山田祥次 先生 修了記念講演

平成22年3月9日(火)
中外日報論説委員
山野上純夫 先生 「『恩讐の彼方に』昇華した物語~啄木の父と高知~」
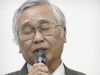
平成22年3月2日(火)
独立行政法人造幣局・造幣博物館前館長
塩川幸男 先生 「貨幣の歴史をたどる」
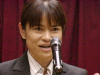
平成22年2月23日(火)
特定非営利活動法人フレンズJAPAN
赤尾和美 先生「カンボジア・アンコール小児病院の10年」

平成22年2月16日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成22年2月9日(火)
学生発表
①26期 大野勝彦さん・28期 松谷敬一さん「福祉ネットワークについて」
②30期 古江常太郎さん「200歳 父母を見守る」
③29期 安田眞琴さん 「112日間 世界一周」

平成22年2月2日(火)
同窓会員招待
岸和田徳州会病院副院長・整形外科医
鄭 明和 先生「健康寿命について~寝たきりにならないために~」

平成22年1月26日(火)
株式会社間口社長
前田克巳 先生 「相撲社会から学んだこと」

平成22年1月19日(火)
東大阪宇宙開発協同組合理事長
杦本日出夫 先生 「やりました夢の実現 まいど衛星」~ものづくりは人づくり~

平成22年1月12日(火)
琴演奏家
前田琴瑟 先生 新春オープニング「琴の音を楽しむ~日本と中国の琴~」

平成21年12月8日(火)
郷土史家
玉谷 哲 先生「泉州を語る②」─秀吉の時代─
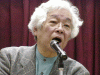
平成21年12月1日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成21年11月24日(火)
将棋9段
有吉道夫 先生「81路の将棋人生」

平成21年11月17日(火)
わらじ医者
早川一光 先生「人間ばんさい!」
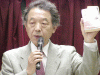
平成21年10月27日(火)
毎日新聞特別編集委員
岡本健一 先生 「童謡『かなりや』の誕生」─西條八十と『古事記』の物語─

平成21年10月20日(火)
スポーツキャスター
西澤 暲 先生「アナログ時代を喋り続けて スポーツアナ55年」
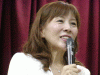
平成21年10月6日(火)
タレント
永田之子 先生「中高年のお洒落&身だしなみ」

平成21年9月29日(火)
日本体育協会公認 体操上級指導員
清水幸恵 先生 「転ばぬ先の筋力アップ」
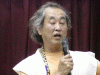
平成21年9月15日(火)
毎日新聞元論説委員
梶川 伸 先生「遍路とお接待」
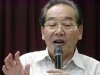
平成21年9月8日(火)
専任講師
小山 昇 先生 古典への招待(29)「日本歴史物語 万華鏡」─安倍晴明とその時代─

平成21年9月1日(火)
同窓会員招待
同志社大学名誉教授
廣川勝美 先生「私たちへの神と仏の言葉」
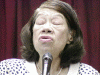
平成21年8月25日(火)
夏季公開講座 グローバルに ローカルに③
女 優
新屋英子 先生 演じ続けて半世紀「身世打鈴(しんせたりょん)」とともに
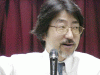
平成21年8月4日(火)
夏季公開講座 グローバルに ローカルに②
東京国際大学准教授
阪口規純 先生「オバマ政権誕生後の世界と日本」

平成21年7月28日(火)
夏季公開講座 グローバルに ローカルに①
大阪管区気象台気候・調査課
足立謙一 先生「地球温暖化について」
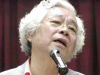
平成21年7月21日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
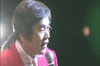
平成21年7月14日(火)
プログラム作成委員会編
「≪ライブ≫きみまろ」─DVDで人気の秘密を探る─

平成21年7月7日(火)
京都大学大学院理学研究科准教授
北井礼三郎 先生「母なる太陽の素顔」

平成21年6月30日(火)
高野山真言宗潮音寺住職
南岳裕史 先生「思い出の人々」
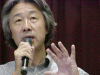
平成21年6月23日(火)
泉南生協協同組合理事長
笠原 優 先生「みのり豊かな老いを」

平成21年6月16日(火)
元気に百歳クラブ関西代表
大澤 須美子 先生「私の元気はどこから」

平成21年6月2日(火)
岸和田警察署
小川昌美 警部補「交通安全教育」

平成21年5月26日(火)
毎日書道展審査会員・書家
森本龍石 先生「書の美 日本の美」

平成21年5月19日(火)
郷土史家
玉谷 哲 先生「泉州を語る①」─織田信長の時代─

平成21年5月12日(火)
浜中医院院長
濱中雄二 先生「おしりはつらいよ」─肛門医からのメッセージ─

平成21年4月28日(火)
本学講師
小山 昇 先生 古典への招待26「日本歴史ものがたり 万華鏡」─怨霊の祟り─
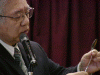
平成21年4月21日(火)
記念講演・同窓会員招待
立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長
安斎育郎 先生「こわい思い込みと錯覚」─振り込め詐欺を防ぐために─

平成21年3月17日(火)
理事長
山田祥次 先生 修了記念講演

平成21年3月10日(火)
精神科医
楠部剛史 先生「心と体の健康」

平成21年3月3日(火)
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成21年2月24日(火)
岸和田警察生活安全課長
山崎文義 警視「振り込めサギに遭わないために」
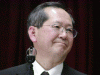
平成21年2月17日(火)
大阪総合会計事務所所長・税理士
清家 裕 先生「消費税はどうなる」

平成21年2月10日(火)
毎日新聞大阪本社社会部 司法クラブキャップ
玉木達也 先生「目前の裁判員制度─どうなる・どうする」

平成21年2月3日(火)
大谷女子大学元教授
入江春行 先生「石川啄木と小林多喜二─格差社会の悩み」

平成21年1月27日(火)
元 建設大臣・観光ボランティア
森本晃司 先生「政界から観光ボランティアへ─元 建設大臣の胸の内」

平成21年1月20日(火)
同窓会員招待
演芸プロデューサー・日本笑い学会副会長
熊谷富夫 先生「笑いは百薬の長」

平成21年1月13日(火)
新春オープニング
ピリアロハ フラ ハラウ
島田智枝 先生「フラで楽しく健やかに」
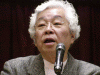
平成20年12月2日(火)
同窓会員招待
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」
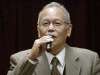
平成20年11月25日(火)
「音で聴く瀬戸内寂聴~生きるとは~」 瀬戸内寂聴を聴く会 編
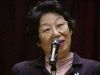
平成20年11月18日(火)
坂東眼科理事長
坂東桂子 先生「加齢と目の健康」

平成20年11月4日(火)
明治生まれの現役ランナー
馬杉次郎 先生「白寿からの青春」

平成20年10月28日(火)
コスモ石油株式会社コーポレートコミュニケーション部広報室(石油連盟広報専門委員)
矢野達也 先生「ガソリンはどうなる 原油は‥‥」

平成20年10月21日(火)
大塚国際美術館学芸部副部長
平田雅男 先生「今だから話せる大塚国際美術館創設裏話あれこれ」-西洋美術史美術館を10倍楽しむ方法-
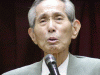
平成20年10月7日(火)
本学講師
浜田禎三 先生「83歳 世界1人旅」

平成20年9月30日(火)
大阪市立大学教授
栄原永遠男 先生「歌木簡は語る─地中からのメッセージ」

平成20年9月16日(火)
大阪センチュリー交響楽団常務理事
出野徹之 先生「大阪センチュリー交響楽団を守れ」
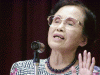
平成20年9月9日(火)
本学講師
野口恵子 先生「暮らしに生きる陰陽五行」

平成20年9月2日(火)
わらじ医者
早川一光 先生「しなやかに老いる」
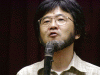
平成20年8月26日(火)
夏期公開講座「世界を知る・日本を学ぶ」③
園田学園女子短期大学部教授
浜口 尚 先生「世界の捕鯨を考える」
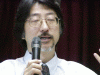
平成20年8月5日(火)
夏季公開講座「世界を知る・日本を学ぶ」②
東京国際大学准教授
阪口規純 先生「日本の安全保障と世界の動き」

平成20年7月29日(火)
夏期公開講座「世界を知る・日本を学ぶ」①
佛教大学教授
小野田俊蔵 先生「日本人にとってのチベット問題」
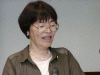
平成20年7月15日(火)
学習発表会 「歌は健老とともに」
乕田良子 先生 「心のうたをうたいましょう」
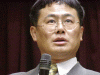
平成20年7月8日(火)
親鸞会講師
山中 徹 先生「縁は異なもの」─釈迦と親鸞の心─

平成20年7月1日(火)
毎日新聞客員編集委員
サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成20年6月24日(火)
岸和田徳州会病院 脳外科部長
大岩美嗣先生 「脳卒中の最新治療と予防」

平成20年6月17日(火)
アドバンス会長
安川昭雄 先生「第2の人生は社会に恩返し」
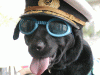
平成20年6月10日(火)
交通安全教育
大阪名物交通安全おじさんこと
嶋田公博さんとラブラドールレトリバー“ワンビー” 「自転車の乗り方」

平成20年5月27日(火)
創立30周年記念講演
理事長
山田祥次 先生「岸和田健老大学の明日」

平成20年5月13日(火)
社会保険労務士
多田 勉 先生「高齢者医療はどうなる」

平成20年4月22日(火)
本学講師
小山 昇 先生「源氏物語」─むらさきの恋─

平成20年4月15日(火)
相馬総合法律事務所 弁護士
相馬達雄 先生「三面記事から学ぶ法律」

平成20年3月18日(火)
本学理事長
山田祥次 先生 修了記念講演
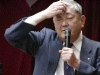
平成20年3月11日(火)
毎日新聞編集委員
玉置通夫 先生「オリンピック物語」
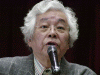
平成20年3月4日(火)
毎日新聞客員編集委員
サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成20年2月26日(火)
日本高野連顧問
永野元玄 先生「マスク越しに見た高校野球から」─ 野球よもやまばなし ─
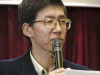
平成20年2月19日(火)
月山 渉 先生「白川上皇の熊野詣と伝説」

平成20年2月12日(火)
大阪府警科捜研前所長
荒砂正名 先生「科学捜査と私のポリグラフ人生」
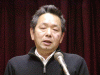
平成20年2月5日(火)
洋画家(美術クラブ講師)
北村 暢 先生「ドイツ美術紀行」
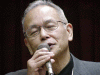
平成20年1月29日(火)
学長
鶴田隆志 先生「流行語でたどる健老30年」
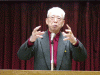
平成20年1月22日(火)
帝塚山大学名誉教授
伊原吉之助 先生「親日国台湾の現状」

平成20年1月15日(火)
同窓会員招待
古代音楽研究家・箏曲家
安部 遼 先生「古代の音色」-お話と演奏-
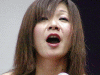
平成20年1月8日(火)
新春コンサート「新春の光に包まれて」
CureVocal 摩耶明子 さん
Piano 田中浩之 さん

平成19年12月4日(火) 同窓会員招待
毎日新聞客員編集委員・サンデー毎日元編集長
八木亜夫 先生 八木亜夫の「世相を斬る」

平成19年11月27日(火)
和歌山大学教授
堀内秀雄 先生「地方自治の課題」
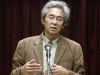
平成19年11月20日(火)
神戸山手大学教授
河上邦彦 先生 「高松塚壁画の意義と解体」

平成19年11月13日(火)
本学学長
鶴田隆志 先生「老人力と鈍感力」
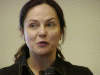
平成19年10月30日(火)
日本ハイパーサーミア学会指導教育者
バレンチナ・オスタペンコ 先生「最近のがん治療について」

平成19年10月23日(火)
現代アート作家
植田睦雄 先生「ほんとうは面白い現代美術」

平成19年10月16日(火)
「ことば&書」作家
辻 慶樹先生「ことば&書のふれあいを大切に」
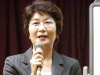
平成19年10月2日(火)
市立岸和田市民病院看護局長
森本一美 先生「医療現場は今」

平成19年9月25日(火)
大阪市立大学名誉教授
中川康一 先生「地震列島日本」

平成19年9月18日(火)
栄養管理士
小林久雄 先生「食と健康」

平成19年9月11日(火)
関西大学法学部教授
山野博史 先生「逆説としての日本近代」
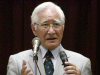
平成19年9月4日(火)
日本スマイリスト協会会長
近藤友二 先生「高齢者を光齢者に」

平成19年8月28日(火)
夏季公開講座「東アジアの隣人たち」③
大阪ソウル会事務局長
本田雅嗣 先生「日朝関係の歴史と課題」

平成19年8月21日(火)
夏季公開講座「東アジアの隣人たち」②
京都外国語大学教授
彭 飛(ポンフェイ) 先生「中国の現状と最新情報」

平成19年8月7日(火)
夏季公開講座「東アジアの隣人たち」①
岡山理科大学准教授
阪口規純 先生「日本外交と東アジア共同体構想」
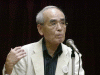
平成19年7月17日(火)
電車博士(本学学生)
天野昌明 先生「電車のおはなし」
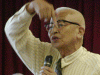
平成19年7月10日(火)
総合人間研究所所長
早川一光 先生「“わらじ医者”老いを語る」

平成19年7月3日(火)
毎日新聞客員編集委員
八木亜夫 先生「最近の日本と世界情勢」
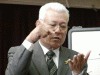
平成19年6月26日(火)
全日空元機長
乙訓昭法 先生「続・知られざるパイロットの世界」
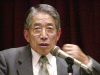
平成19年6月19日(火)
日本アイアンマンクラブ会員
浜島範年 先生「トライアスリートの心」
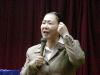
平成19年6月5日(火)
岸和田警察署 交通安全教育
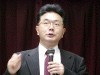
平成19年5月29日(火)
社会保険労務士
多田 勉 先生「高齢者のこれからの医療・介護保険制度の仕組み」
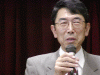
平成19年5月22日(火)
大阪市立大学院前教授
広川禎秀 先生「日本の近現代史を見る目」

平成19年5月15日(火)
ダイナミックスポーツ医学研究所副所長
土井龍雄 先生 「ウォーキングWALKING」
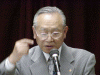
平成19年5月8日(火)
関西フィル元代表
大川真一郎 先生「クラシックへの誘い」
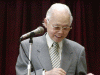
平成19年4月24日(火)
樟蔭女子短大名誉教授
森田康夫 先生「貝原益軒の『養生訓』を読む」

平成19年4月17(火)
本学学長
鶴田隆志 先生「老楽学のすゝめ」
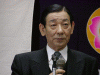
平成19年3月20日(火)
本学理事長
山田祥次 先生 修了記念講演「健やかに生きる」
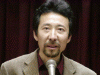
平成19年3月13日(火)
モンゴルの里村長
スーチン・ドロン 先生「モンゴル事情」

平成19年3月6日(火)
毎日新聞客員編集委員
八木亜夫 先生「最近の日本と世界情勢」

平成19年2月27日(火)
関西電力地域共生・広報室マネージャー
真嵜康行 先生 「最近のエネルギー問題と電力事情」
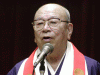
平成19年2月20日(火)
紀三井寺貫主
前田孝道 先生 「現代の世相と宗教」─観音信仰を中心に─

平成19年2月13日(火)
NPO法人高槻オレンジの会理事長
岸本昌三 先生 「生きる」─わが人生・情熱と共に─

平成19年2月6日(火)
堺市立堺病院名誉院長
里見 隆 先生 「人間ドックで"○○が高めですよ〟と言われた人のために」
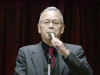
平成19年1月30日(火)
本学学長
鶴田隆志 先生 「『いくつになっても脳は若返る』から」

平成19年1月23日(火)
宝塚・アフガニスタン友好協会
西垣敬子 先生 「アフガニスタン情報」 草の根からの報告

平成19年1月16日(火)
歌声喫茶 筒井幹夫 先生
ピアノ・アコーディオン 塩入哲郎 先生 「青春のうたごえIN健老」

平成19年1月9日(火)
新春コンサート
オカリナバンド KOYA 三宅省一郎さん

平成18年12月12日(火)
大阪地検岸和田支部支部長
内井啓介 先生「裁判員制度とは」
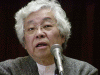
平成18年12月5日(火)
毎日新聞客員編集委員
八木亜夫 先生「最近の日本と世界情勢」
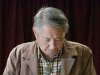
平成18年11月28日(火)
小林利郷 先生 泉州地方の伝説「ちぬの海ものがたりⅡ」

平成18年11月21日(火)
㈱NTTドコモ関西マーケティング本部 営業企画部
営業企画担当課長 松村祐一 先生
営業推進担当課長 西本 匠 先生
「ケータイの今と未来」─番号ポータビリティによせて─

平成18年11月14日(火)
松永直子 先生「与謝野晶子に魅せられて」
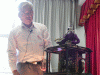
平成18年10月31日(火)
細井清司 先生「からくり人形とものづくり」
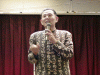
平成18年10月24日(火)
口笛音楽奏者
もく まさあき 先生「口笛で楽しく健康に」

平成18年10月17日(火)
和泉史談会代表
小林利郷 先生泉州地方の伝説「ちぬの海ものがたり」

平成18年10月3日(火)
葛城市歴史博物館学芸員
神庭 滋 先生「遺唐留学生・井真成の故郷は」─竹内遺跡が語るものは─
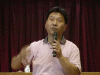
平成18年9月26日(火)
奥 幸博 先生「介護予防」─認知症に活かす─

平成18年9月19日(火)
大原正義 先生「阿倍仲麻呂伝 」

平成18年9月12日(火)
阪神タイガース専属レポーター
唐渡吉則 先生「放送30年 阪神タイガースとともに!! 」
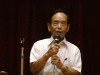
平成18年9月5日(火)
前岸和田市長
原 曻 先生「地方自治32年 」

平成18年8月22日(火)
夏期公開講座「国際紛争にゆらぐ日本」③
中外日報論説委員
山野上純夫 先生「一神教と多神教のはざま 」

平成18年8月8日(火)
夏期公開講座「国際紛争にゆらぐ日本」②
龍谷大学教授
越前谷 宏 先生「近・現代文学に見る『戦争と平和』 」─井伏鱒二『黒い雨』中心に─
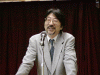
平成18年8月1日(火)
夏期公開講座「国際紛争にゆらぐ日本」①
岡山理科大学助教授
阪口規純 先生「世界のなかで日本は今」
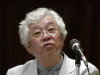
平成18年7月18日(火)
毎日新聞客員編集委員
八木亜夫 先生「最近の日本と世界情勢」

平成18年7月11日(火)
NPO法人WACわかやま理事長
中村富子 先生 「100歳をめざして 」
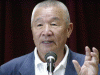
平成18年7月4日(火)
大阪府マリーナ協会相談役 ヨットマン
鹿島郁男 先生 「77歳の挑戦─単独世界一周の航海へ」

平成18年6月27日(火)
月山 渉 先生 泉南の「 藤 代 」

平成18年6月20日(火)
(社)日本ウォーキング協会講師
畑中一一 先生 「英国で一番美しい町や村々」─コッツウォルズを歩く旅─

平成18年6月6日(火)
交通安全教育 岸和田警察
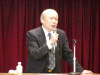
平成18年5月30日(火)
大阪府臨床心理会 会長
梶谷健二 先生 「心の健康」 人と人との関係を考える

平成18年5月23日(火)
岸和田市教育委員会生涯学習課
寺田 博 先生 「地域社会が支える子供の安全」

平成18年5月16日(火)
岸和田消防本部消防指令補
田中健次 先生 「防災力を高めよう」
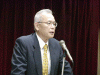
平成18年5月16日(火)
本学学長
鶴田隆志 先生 「健老新時代」
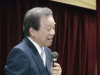
平成18年5月9日(火)
和歌山生涯学習協議会
村田溥積 先生 「生命の尊さと人間の誇りを」─あなたにしかできない事がある─
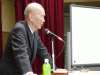
平成18年4月25日(火)
前学長
村田義人 先生 「言い残したこと やり残したこと」
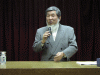
平成18年4月18日(火)
日本笑い学会副会長 元気で長生き研究所所長
昇 幹夫 先生 「元気で長生きPPKのコツ」
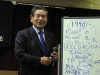
平成18年4月11日(火)
(財)日本サッカー協会キャプテン
川淵三郎 先生 「ドイツへの道」

平成18年3月14日(火)
修了記念講演
本学理事長
山田祥次 先生 「生命を観る人間を観る」
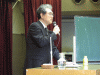
平成18年3月7日(火)
国際東洋医療鍼灸学院副学院長
坂本豊次 先生 「健康管理のツボ療法」
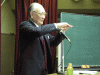
平成18年2月28日(火)
学生発表「健老大学と私」
寺川チサトさん 「健老大学と私」
伊藤阪夫さん 「天照大神について」
吉村 貢さん 「近畿よいとこ 泉州一番」
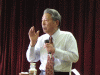
平成18年2月21日(火)
小林利郷 先生 「泉州の民話」
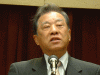
平成18年2月14日(火)
和歌山生涯学習協議会
村田溥積 先生 「華やいで輝いて」─厳しさと優しさ─

平成18年2月7日(火)
大原正義 先生 「唐の都 長安に馳せる夢 望郷の想い 阿倍仲麻呂
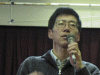
平成18年1月31日(火)
月山 渉 先生 「歩くということ」

平成18年1月24日(火)
毎日新聞編集委員
玉置通夫 先生 「記者が見た大阪のスポーツ」

平成18年1月17日(火)
元 全日空機長
乙訓昭法 先生 「知られざるパイロットの世界」

平成17年12月13日(火)
元 藤井寺高校々長
森井久夫 先生 文学の世界「小林一茶の世界」
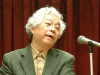
平成17年12月6日(火)
毎日新聞客員編集委員
八木亜夫 先生 「最近の日本と世界情勢」
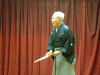
平成17年11月29日(火)
いづみ健老大学学長
戸神繁一 先生 お話しと一人狂言「萩大名」

平成17年11月22日(火)
本学学長
村田義人 先生 貝原益軒「和俗童子訓」」
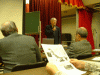
平成17年11月15日(火)
環境省自然公園指導員
畑中一一 先生「伊能忠敬と『伊能ウォーク』が遺したもの」

平成17年11月8日(火)
弁護士
相馬達雄 先生 「世相と法律」

平成17年10月25日(火)
うえむら牧場代表
黒瀬礼子 先生 「小さな町の牧童たち」

平成17年10月18日(火)
元 大阪城天守閣館長
渡辺 武 先生 「豊臣秀吉を語る」

平成17年10月4日(火)
文部科学省選定映画 「NITABO」
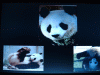
平成17年9月27日(火)
天王寺動物園 園長
宮下 実 先生 「移り変わる動物園」
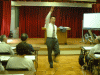
平成17年9月20日(火)
全日本車椅子バスケット総監督
高橋 明 先生 「共に生きる」 障害者のスポーツを通して